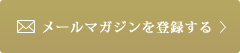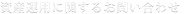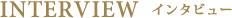わざと“隙”を見せるコミュニケーション術とは?

2020.06.25
映画監督:ウエダアツシ氏インタビュー
「リュウグウノツカイ」で注目を集めた映画監督・ウエダアツシ氏。
その後も、小芝風花、横浜流星を主演に迎えた「天使のいる図書館」(2017年)など話題作を送るウエダ氏に、生い立ちから、多くの人数が関わる映画撮影現場の長としての心構えなどを聞いた。
独学を貫いたからこそ型にはまることはない
ウエダ アツシ氏(以下、ウエダ)「奈良県出身なのですが、地元の高校を卒業後、近畿大学に進学しました。映画部に所属し、自主映画の制作に明け暮れていましたね。大学内で誰よりも撮っていたと思います。今思えば、とても人に見せられるようなものではないですが…(笑)」
ウエダ「関西の情報誌で映画ページの制作に携わりました。その後、2002年に上京することになったのですが、その頃はやはり本来好きな映像に関わる仕事がしたいという欲が出てきた時期だったんです。ちょうどWEBメディアが躍進し始めた時で、紙の情報誌からWEBの情報サイトに職場が変わり、いつの間にか芸能人の記者会見の模様を撮影し、それを編集して配信することが僕の仕事になりました。これまで趣味でしかなかった映像制作が仕事に繋がったのはとにかくうれしかったですね」
ウエダ「『いずれ撮りたい』とは思っていたのですが、正直、目の前の仕事でいっぱいいっぱいで、そこまで目が向けられていなかったです。その後、映画のメイキング映像制作(DVDの特典などで使用する映像)で、さまざまな現場に出入りするようになりましたが、監督の演出やキャスト、スタッフとの接し方は十人十色なんですよ。僕は助監督経験がありませんので、その時にたくさんの映画制作のノウハウを学ぶことができました」
ウエダ「映像や脚本の専門学校に行くことを考えたこともありました。しかし、いざ〝勉強する〟となると、ぜったいにサボると思ったんですよ、大学は経済学専攻でしたがサボりまくったあげく5年行きましたし(笑)。ですので、映画はずっと趣味のままやり続けるか、実際に仕事として現場で学ぶかの2択しかなかったですね。今考えると、東京に来て映像の仕事ができる足掛かりを作れたことはものすごく幸運でした。それに、変に学校で学ばなかったからこそ、自由な発想が生まれている部分もあるのかもしれません」
日常に戻ることを信じ企画を練り続ける
ウエダ「当時、同居していた映像制作の先輩が独立して起業されたんです。そのタイミングで、何か名刺代わりになる作品をということで制作が始まりました。僕も35歳になっていて、だらだらと現状の生活を続けてもいられないという、焦りではありませんが、チャレンジしてみたい気持ちが高ぶっていたんです。完全自主制作の映画でしたが、『ゆうばり国際ファンタスティック映画祭』で北海道知事賞をいただいたことを機に劇場公開もされました」
ウエダ「まぁ、見てきた知識と、実際にやってみて得られたものとの差異はたくさんありましたが、〝わからないことはわからないと言おう〟という、ある意味での開き直りがありました。女子高生の集団が登場する物語ですが、はっきり言って35歳で10代の女の子の心情なんてわからないじゃないですか(笑)。ですので、キャストの子に『監督、今の女子高生はこんな喋り方しませんよ』なんて言われると、その場でセリフを変えたり、臨機応変に対応して。そうすると、自分の意見が通るものだから、若いキャストの子たちも生き生きとしてくるんですよ。結果的に、女子高生の集団の距離感や〝ワチャワチャ感〟がよりリアルに出ましたね」
ウエダ「もちろん、責任感というものも増えましたが、そこまで大きくは変わっていないです。次作でいきなり助監督が20近く年上のベテランの方になって、ちょっとやりにくいな…くらいでしょうか(笑)。先ほども言いましたが、そもそも僕は助監督経験もない、前作でたまたまラッキーパンチが当たったみたいな人間。正直、セオリー的なことは全く知りませんでした。だけど、経験が豊富なスタッフに言われるがまま作っていても面白くない。いかに自分の個性を生かしていくかということは、常に念頭には置いていましたね」
ウエダ「映画制作って関わる人数が多い割に、期間はすごく短いんです。なので、キャストやスタッフと上辺だけではない、より深い会話やコミュニケーションをいかに早く行えるようになるかが勝負だと思っています。僕は、こちらが〝隙〟を見せるしかないと考えています。いい格好をせず、普段通りの僕で立ち居ふるまうというか…。例えば、現場にビーチサンダルで出向いたり(笑)。若ければ若いほど、カッチリした大人って話しかけづらいものですからね。なるべく若いキャストやスタッフに、年齢や立場を超え、気軽に話しかけてもらえる監督でいたいと思っています、自分が歳を取るほど若い人の意見は貴重ですしね。それと、叱り方には気を付けています。僕は演技面や技術面で叱ることはありません。もっと、常識的なことというか、役者さんや撮影場所を提供してくれる方などに対しての礼儀や態度とか、チームとしての輪を乱す行為だとか、秩序を守れないだとか、そういったことに関してだけ叱るようにしています。もちろん、叱るからには自分自身がしっかりできていないといけないので、現場に誰よりも先に入ったりなどは心掛けています」
ウエダ「東日本大震災時にも思いましたが、我々にできることはいったい何だろうと模索しています。間違いなく今後、物を作るうえでの影響は出てきますよね。当たり前だった日常というものがなんて素晴らしいことだったのかを痛感していますし、僕自身もコロナウイルス騒動以前に考えていた物語の構想のいくつかは白紙に戻さざるを得ない、それぐらい価値観が変わってしまいました。しかし、エンターテインメントの未来を考えるならば、現在の自粛や自重はもちろん大事ですが、あまり過剰になりすぎるのも危険ではないでしょうか。例えば、それまで普通に描かれていたキスシーンが『これは濃厚接触だ、けしからん』という意見が出れば、それは異常ですよね。だから、いずれ正常に戻ることを信じ、それを大前提に、これまで通りの〝正常な映画〟の企画を練ることが、今の僕がすべき〝ステイホーム〟だと思っています」
●ウエダ アツシ
1977年8月22日生まれ、奈良県出身。近畿大学時代から映画を制作し、雑誌編集者などを経て2014年、「リュウグウノツカイ」で長編映画監督デビュー。「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2014」で北海道知事賞を受賞し頭角を現す。ほか、監督作に「桜ノ雨」(2016年)、「天使のいる図書館」(2017年)、「富美子の足」(2018年)、「ジャンクション29」(2019年)などがある。