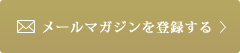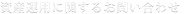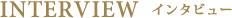暑苦しいほどに本と向き合うベテラン編集者の仕事への情熱

2017.05.17
編集者 秋藤幸司氏インタビュー
●編集者
1963年生まれ。広島市出身。大学卒業後、若林出版企画、宝島社、エクスナレッジ、角川書店を経て、2010年より現職。『男はつらいよ 寅さんDVDマガジン』『山口百恵 赤いシリーズDVDマガジン』などを担当するかたわら、政治・経済から絵本まで、幅広いジャンルの書籍編集も手がける。現在は、DVD付き英語教材『週刊おもてなし純ジャパENGLISH』をメインに担当中。
ファッション誌にあこがれて出版社の門をたたくも…
秋藤幸司氏(以下、秋藤):小学校から高校まではサッカーばかりしている子供でした。まぁ、ずっとベンチを温めているいわば補欠でどうしようもなかったですが(笑)。サッカーに情熱を傾けるその一方で、76年に雑誌『ポパイ』が創刊されて、すっかり雑誌の中の世界に引き込まれてしまったんです。
姉の影響で『an・an』も読んでいましたが、そちらも華やかで素敵で…。僕たちの世代にとって、ちょうど雑誌という文化が熱かったので、いずれ自分もこんなファッション誌を作ってみたい、という淡い思いはその頃から抱いていましたね。
秋藤:ファッション誌への強いあこがれを抱いて、出版社を中心に就職活動をするのですが、私はどうもヘソ曲がりで、自信過剰だったので…。
友人が大手出版社に就職したと聞いたら『だったら俺は小さいところから叩き上げで上り詰めてやる』と、大学を卒業してすぐに就職したのは、ほとんど顔パスみたいな感じで入れた小さな出版社でした。
今思えば本当に陳腐な話ですが(笑)。しかし、その当時は、アルバイト情報誌の冒頭の特集ページを作るなど、出版社というより編集プロダクションの業務がメインだったので、一年くらい働いていると『ここは何か違うぞ』と感じるようになってしまったんです。
結局二年くらい勤めた後、縁があって宝島社(当時はJICC出版局)に誘っていただいて転職を決めました。今でも発行されている『田舎暮らしの本』などを編集していましたが、やはり雑誌が作れるという喜びは大きかったですね。
秋藤:いわば原点ですね。宝島社で編集者として鍛えられて、成長させてもらいましたので。今こうして編集者でいられるのは、あの頃の経験があるからだと思っています。
しかし結局、その後に宝島社も辞めて、そこから業界誌をやったり、情報誌をやったり、大阪に転勤したり…講談社に落ち着くまで、流浪することになるんですよね(苦笑)
秋藤:一時期は、自分で作った“大人も楽しめるファッション・カルチャー誌”の企画書をずっと持ち歩いたりしていた時期もありましたが、長い編集者人生で、考え方も随分と変わりましたね。その一つのきっかけが、若い頃、先輩編集者から言われた一言でした。
その先輩は、写真集を作らせたら右に出る者はいないほど優秀で、当時から売れっ子だったアラーキーこと荒木経惟さんとも懇意にされていたんです。
ある日、私が『荒木さんと仲が良いんだったら、荒木さんの写真集を出せば売れるじゃないですか? 』と聞いたら『そんなものは、俺が出さなくても誰かが出す。俺はまだ世に出ていない才能のある写真家の写真集を作りたい。才能のある奴はたくさんいるんだ! 』と言われたんです。
当時はいまいち“誰もやらないことをやる”ということの意味を理解しきれていませんでしたが、今では僕の編集者人生の核となっている言葉ですね。
編集者とはいわば“表現者”会社との折り合いの付け方
秋藤:著者の飯塚雅俊さんのブログを読んで興味を抱き、実際にお会いしてすごく感銘を受けたんです。結局、社内で企画を通すのに五年近くかかってしまいましたが…まさに、俺がやらなきゃ誰がやる、という気持ちだけでしたね。それくらい、どうしても出版したかった本です。
秋藤:本来の編集者という仕事と会社員という立場はあまり親和性がないと思っています。もちろん、長く会社にいるとどうしてもやりたくない仕事もやらないといけないことが少なからずありますし、人を育てるということも会社が私に求める仕事の一つだとは思っています…。
でも、私は、編集者はある意味で表現者であると思うんです。作家やカメラマン、デザイナーの力を借りて自己を表現する。やはり、若いころに影響を受けた先輩編集者たちの教えが染みついているんでしょう。暑苦しい男ですよ、本当に(笑)
もちろん、組織なので自己表現をし続ける姿勢を維持していくのが難しい時もあります。清濁併せ呑むというか、妥協をしないといけない場面もあります。例えば、売れ線を狙って本を作ってみたり…しかし、先ほども言いましたが『闘うもやし〜』に関しては、自分のやりたいことを押し通させてもらいました。
バランスという意味では、絶対やりたいことを押し通す分、ほかではちょっと売れ線をやってもいいかな、と思うところは正直ありますね。…しかし、会社的には私みたいなややこしい編集者、目の上のたん瘤だと思いますよ(笑)
秋藤:私のモットーは“生涯現役”。別に編集者じゃなくてもいいんです。実家のクリーニング店を手伝ってもいい。
しかし、仕事をしていないと、人としての存在意義がないと感じます。いずれにせよ、出したい本の企画はまだまだ山ほどあるんです。企画は何か社会に感じるものがあれば自然と生まれるので、逆にそういったものが出てこなくなったら編集者としてはひと段落かなと思っています。
それまでは、自分の持っている才能というか、才能らしきものを使って、相も変わらず暑苦しく本と向き合い続けたいですね。
秋藤氏が手掛ける主な本
闘うもやし-食のグローバリズムに敢然と立ち向かうある生産者の奮闘記-
埼玉県・深谷市で親子二代、50年にわたってもやし栽培業を営む飯塚商店の飯塚氏は、大手スーパーから「今どきの大量生産もやしを作るか、従来のもやし作りにこだわるか」と迫られ、後者を選んだために取引中止に。経済的大打撃を受けながらも、それでも“当たり前のきちんとした本来のもやし”を作り続ける決意をした飯塚氏とその家族の闘いをユーモアを交えてつづる。
週刊おもてなし純ジャパENGLISH
純ジャパ(=海外の経験がない人)でも、簡単に英語が話せるようになる!? 英語を話している全人口の中でネイティブの英語を話す人はわずか20%未満。なんと80%以上が非ネイティブの英語を話しているという。非ネイティブの英語は中学校2年生レベルの知識で会話が可能…そこで、居酒屋メニューからポップカルチャーまでシチュエーションごとに会話例をDVD付きで紹介する。
安河内哲也 著
講談社/1642円
(創刊号のみ821円)/発売中