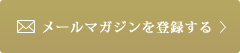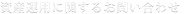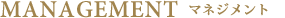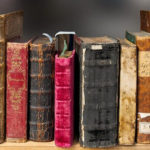お店の在庫管理とビジネスマンの収納術から学ぶ物品管理

2016.03.09
在庫管理Vol.1 -保管場所を見直すと効率が上がる-
・治療スピードがアップし、効率がアップする
→治療件数を増やし、人件費を抑える
・デッドストックをなくし、材料のムダを抑える
→経費削減
・不要なものをなくし、院内がスッキリ清潔に保ちやすくなる
→衛生管理
改善の余地がないか、年に1度、収納場所や管理方法の見直しされることをお勧めします。そこで今回は、他業界で徹底されている収納ルールから学ぶ、在庫管理についてご紹介いたします。
飲食店「古いものを前へ」
飲食店やスーパーで扱う生鮮食品は、刻一刻と価値が下がっていきます。そのようなお店では、食品を「先入れ先出し」と言って、先に仕入れたものを先に売りきるのが常識となっています。
◆先入れ先出しを徹底
歯科材料も同じです。高額で、かつ消費期限のある材料を、ムダなくきちんと使いきるために、届いたものは在庫より奥に収納するよう、スタッフに徹底しておくことが大切です。
100円ショップ「在庫の数を決める」
限られた店内のスペースで、最大限に売り上げる必要のある100円ショップ。実は在庫を置き過ぎないことが、重要なポイントとなっているようです。
よく売れる商品と、かさばる商品だけは、店舗の後ろの在庫スペースに置きますが、それ以外の一般商品は、陳列棚に入るだけをストックして、それ以上は在庫を持たないよう徹底しています。一見、販売の機会を損失しそうですが、100個などの大口は、注文予約で対応しています。
これと同じことを、歯科医院の在庫管理で考えるとどうなるでしょう。
◆倉庫や在庫エリアに収納しておくのは以下の2種のみ
・使用頻度の高い材料
(毎日使う消毒などの薬剤、など)
・かさばる材料
(エプロン、ティッシュ、紙コップ、ペーパー類など)
これらは1日で使い切る分量を毎朝出して、使用する場所の近くに配置するか、診療中の導線内に置く場所を決めておくとよいでしょう。
◆通常の材料は使用場所にまとめてストック
それ以外の材料は、使いかけのものも、新品の在庫も、全て同じ場所にストックしておくことで、一目で把握できるようになります。残りの数量を誤ったり、ダブって注文したりすることがなくなります。この時に前述の「先入れ先出し」を徹底するようにします。
また「残り○個になったら発注」など、メモを棚に貼っておくと、発注のタイミングがわかりやすくなります。ムダを防ぐことで、材料費の損失を避け、経費削減につながります。
ビジネスオフィス「仕事内容ごとに収納」
機能を重視して作られたビジネスデスク。天板の下の広くて薄い引き出しは、処理中の書類を入れるようになっています。
右1番上の薄い引き出しには小さな文具を入れ、特に手前には使用頻度の高いものを入れ、奥に向かって頻度の低いものを収納すると、効率よく出し入れすることができます。その下の引き出しには、名刺などの小物を入れ、1番下の深い引き出しには、長く保管し、たまに確認する書類などを立てて収納します。
◆作業内容の同じものをまとめる
・シンクの下の高さがある収納には、清掃用具や洗剤類をまとめて入れる
・同じ処置で使うものは、同じ場所、または近くに収納する
・診察で使うバー類やカートリッジは、ユニットの近くの薄い引き出しに小型容器に分類して名前のシールをつけておき、すぐ先生に渡せるようにする
◆受付のデスクをスッキリさせる
・同じような余分な文具があれば整理する(ペンや古い印鑑など)
・処方された薬はすぐに出せるよう、適量をまとめて保管する
◆入れすぎない
また全ての収納で言えることですが、「ぎっちり」詰め込むと、出し入れが大変になります。空間の中にしめる物の量を80%…可能なら60%ほどに抑えると、誰でも瞬間的に出し入れができて、効率がアップします。
◆新人がすぐ把握できる状態に
新人スタッフがもたつかずに動ける状態なら、全てのスタッフが動きやすい治療室だといえるでしょう。「口を開けたまま待たされてイライラした」「治療に時間がかかる」という患者さんの不満をなくすこともできます。同じ時間内でより多くの治療を行って収入を増やすことができますし、効率があがることで、人件費の節約にもなります。
また収納をスッキリさせることで清掃もしやすく、清潔な院内を維持しやすくなります。
まとめ
いかがでしょうか? すでに医院で取り入れている、という技法も、いくつかあるかもしれませんね。しかし、治療法や材料の変化にともなって、10年前とは管理方法が変わっているケースも多いようです。
ぜひ、準備にもたつきがないか? 材料の廃棄がないか? など、振り返ってみることをおすすめします。
また、スタッフに一度「材料や器具の収納で、困っていること、変えたほうがいいことはある?」と聞いてみると、新たな改善点を発見できるかもしれません。小さな変化で、診療の効率が飛躍的にあがることも少なくないのです。