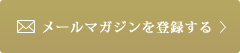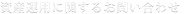開業医は遺言書で何をすればよい?遺言書が重要となる6パターン

2016.11.08
開業医が遺言書を作成しておくべき6つのパターン
遺産分割でもめないために有効なのが遺言だと言われていますが、実際に準備する人はまだまだ少ないのが実情です。
今回の記事では、開業医のみなさまが「遺言書」の準備をしておきたい6つのケースについて紹介していきます。まずは、遺言で何ができるのか、その基本について解説し、具体的なケーススタディをしていきます。
それぞれのケースに合わせて、開業医のみなさまご自身にあてはまる内容をお役立ていただければと思います。
・そもそも遺言書で何ができるのか
・①相続人である子どもが複数いて、兄弟仲が悪い場合
・②亡くなった人(被相続人)に、子どもがいなかった場合
・③先妻との間に子どもがいる場合
・④遺贈をする場合
・⑤マイナスの財産がある場合
・⑥事業を営んでいる場合
そもそも遺言書で何ができるのか
遺言書でできることは数多くありますが、最も多く利用されるのは、相続分の指定です。相続には法定相続分という考え方があります。相続人が配偶者と子どもの場合は、それぞれ2分の1が法定相続分となります。子どもが複数いる場合には、2分の1を子どもの人数で均等にわけます。
遺言書がない場合には、法定相続分で分けるのが基本ですが、特定の相続人に法定相続分よりも多く分割したい場合には、遺言によって「相続分の指定」を行うことができます。
しかし、相続人には「遺留分」という遺言でも侵せない権利がありますので、それを無視した遺言を書いてしまうと逆にトラブルのタネをまいてしまうことになります。詳しくは追ってご紹介します。
また、遺言では「遺贈」も可能です。遺贈とは、相続人以外の人に財産を残すことです。
「老後に世話になった長男の嫁に財産を残したい」「孫に財産を残したい」などのほか、「愛人に財産を残したい」というケースも実は少なくありません。遺言で財産を寄付することも可能です。
遺言によって最大5年間、遺産分割を禁止することも可能です。例えば、相続人の1人が海外赴任中で遺産分割協議に参加できない場合や相続人に学生がいて卒業するまでは学業に専念させるために、一定期間遺産分割を禁止することなどができます。
さらに、遺言によって子どもの認知や生命保険の受取人の変更などを行うこともできます。
遺言がなければ、相続人は全員が揃って遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議でもめてしまうと、いつまでたっても分割ができません。
しかし、遺言があれば、遺産分割協議の必要はありませんので、スムーズに遺産分割ができます。相続人の負担もそれだけ軽くすることができるのです。
続けて、特に遺言を書いた方がよい6つのケースについて解説します。
①相続人である子どもが複数いて、兄弟仲が悪いケース

相続が発生した際にトラブルが起きそうなケースでは、遺言の効果が発揮されます。最もトラブルの発生しやすいケースは、相続人である子どもが複数いて、兄弟仲が悪いケースです。
相続が発生すると、相続人は遺産分割協議を行い、誰が何をどれだけ相続をするか話し合いを行わなくてはなりません。兄弟仲が良くても遺産分割協議でもめてしまうことはよくありますが、もともと兄弟仲が悪い場合、恨みつらみが相続で吹き出し、収拾がつなかくなってしまう可能性があります。
遺産分割のトラブルは、単なる金銭面のトラブルだけでなく、それまでに蓄積された互いの不満が背景になっているケースが少なくありません。弟が「兄貴は留学までさせてもらったじゃないか」と言えば、兄は「おまえは家を買うときに半分出してもらったじゃないか」というなど、他の兄弟が親にしてもらったことはよく覚えているものです。
そこには金額の問題だけではなく、「自分より兄貴のほうが父親にかわいがられていた」など、子どもの心情も大きくかかわっているだけに後には引けない状況ができてしまいます。
そのようなことが考えられる場合、遺言で親が誰に何を相続させるのかを指定し、なぜ、そのような配分にしたのか、親の意志も残すとトラブルを避けやすくなります。
遺言には、付言事項といって、親の気持ちを言葉にして記載することができます。例えば、長男に対して「最後までよく面倒を見てくれてありがとう。苦労をかけたから預金を多めに残す」などと記せば他の兄弟も納得しやすいでしょう。
遺産分割協議で解決しないと家庭裁判所に持ち込まれ、遺産分割調停や審判などになることもあります。そうなると解決するまでに時間も労力もかかります。兄弟仲がさらに悪くなり、その後は「一生会いたくない」ということにもなりかねませんので、遺言で親の意志を示し、無駄なトラブルを避けるのがよいでしょう。
②亡くなった人(被相続人)に、子どもがいなかった場合

遺言がない場合、遺産分割は法定相続分をベースに決めることが多くなりますが、亡くなった人(被相続人)に、子どもがいなかった場合にはどうなるでしょうか。
被相続人の両親が健在の場合には配偶者の法廷相続分が3分の2、両親が3分の1となります。
しかし、一般的に考えれば、両親のほうが先に亡くなっているでしょうから、その場合には、配偶者が4分の3、被相続人の兄弟姉妹が4分の1の法定相続分を受け取ることになります。兄弟が複数いる場合には、4分の1を兄弟の人数で分けることになります。
配偶者にとってみれば、夫婦で築いた財産を義理の兄弟姉妹に分けなければならないのです。義理の両親なら、まだ納得ができる面もあるかもしれませんが、義理の兄弟とは疎遠になっていることも多いでしょうから、複雑な心境なはずです。
しかも、義理の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供、つまり甥や姪が相続権を引き継ぐことになります。これを代襲相続といいます。そうなると、相続人の数がどんどん多くなってしまい、遺産分割協議を開くとなっても大変です。
なかには身勝手なことを言う人も出てくるでしょうし、連絡がつかない人も出てくる可能性があります。いつまで経っても遺産分割ができないという事態も考えられます。
子供がいない場合には、ぜひ遺言書を書いておくべきです。通常、相続人には、遺言を書いても侵すことのできない遺留分という権利があります。たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、子どもの遺留分は4分の1です。親不孝な子供に財産を残したくないと考えて遺言を書いたとしても、子どもには4分の1が遺留分として権利が保証されているのです。
ところが、前述のように被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には、遺留分がありません。すべてを配偶者に残すことができるのです。遺言書を書くだけで兄弟姉妹に財産が行かないようにできるのです。
残された配偶者のことを考えるのであれば、遺言は必須といえるのではないでしょうか?
③先妻との間に子どもがいる場合

最近では、離婚後に再婚する人も珍しくありません。そのような場合にも、相続においては注意が必要です。とくに先妻との間に子どもがいる場合には、遺産分割の際にトラブルの原因になることが少なくありません。
離婚して再婚した場合、妻の相続権はすべて新しい妻に移ります。相続上、先妻にはまったく権利がなくなるのです。これは、結婚していた期間は、関係ありません。30年連れ添った夫婦が離婚し、再婚して1年後に亡くなったとしても、妻の権利はすべて新しい妻にあります。
一方で先妻に子どもがいる場合、子どもには、相続権があります。先妻の子も再婚相手の子どもも相続の権利は変わりません。一般的に言えば、先妻の子どもと再婚相手の子どもの仲が良いというケースはまれではないでしょうか。遺産分割の話し合いとなれば、少なからず、もめごとが発生する可能性は高いでしょう。
とくに先妻は、まったく相続権がありませんから、その思いを子どもに託して、遺産分割協議で優位に立とうとしたり、遺産分割を妨害しようとするかもしれません。
遺言があれば、遺産分割協議をせずに相続手続きができますので、余計なトラブルを防ぐことができます。
また、「亡くなった父親に隠し子がいた!」というと、ドラマの中だけの話のような気がしますが、実際の相続でも決して少なくないようです。
隠し子がいることを生前に家族に打ち明けるのは、なかなか難しいものです。ですから、亡くなるまで家族が気づかないことが多いのです。しかし、残された家族の立場に立ってみれば、突然、隠し子が現れたりすれば、精神的なショックもあり、トラブルになる可能性が大きいのです。
隠し子の存在に気づかないまま相続手続きが終わることもあるのではないか、と考える人もいるかもしれませんが、それはあり得ません。
相続手続きの際には、まず、相続人を確定させることから始めますから、被相続人の戸籍をさかのぼって調査をします。認知をした子どもがいれば、必ず判明します。認知されていない子どもに相続権はありませんが、認知されている子どもには相続権があります。
隠し子のことを正式には非嫡出子といい、正妻の子どもは嫡出子といいます。以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、現在ではどちらも同じ権利になっていますから、より深刻なトラブルに発展する可能性があります。
このケースでも遺言があれば、遺産分割協議の必要がありませんから、スムーズに相続手続きが可能です。また、認知していなかった非嫡出子を、遺言によって認知することも可能です。仮に認知ができない場合でも、遺言で財産を残すこともできます。これを遺贈といいます。
④遺贈をする場合

誰が相続人になるのかは法律によって決められていますが、相続人以外に財産を残すことができないわけではありません。遺言を残すことによって、相続人ではない人に財産を引き継ぐことができます。これを遺贈といいます。
たとえば、長男家族と同居をしているような場合、長男の嫁には何かと世話になることもあります。特に介護が必要になった際には、嫁の負担は大変なものです。しかし、何もせずに相続が発生するとどうなるでしょう。嫁は相続人ではありませんから、財産を受け取る権利はありません。
「それなら兄弟で話し合って長男が多めに受け取ればいいじゃないか」と考えるかもしれません。しかし、これがトラブルの元です。次男や長女も、長男が同居して親の面倒を見ていたことは理解していますが、一方で「同居していたメリットもあっただろう」と考えてしまうものです。
「食費や光熱費が助かっていただろう」「旅行に連れていってもらっただろう」という言葉はよく聞かれます。長男にしてみれば、親に気を遣って自由に外食に行けないこともあれば、旅行にいったとしても親の付き添い的な意味合いもあったはずです。
子ども同士の意識にズレがあるので、嫁に感謝の気持ちを示したいのであれば、親が遺言を残し、意思表示をするのがベストです。親が「世話になった嫁に財産を残す」という意思表示をすれば、長男以外も納得するはずです。
遺言によって孫に財産を残すこともできます。通常は、親→子ども→孫と財産が受け継がれますので、相続は2段階になります。相続税も2段階で課税されます。しかし、親→孫と相続が行われれば、1代飛ばしで相続をさせることができて、相続税の支払い回数が減り、節税になる場合があります。ただし、孫への相続は相続税が2割増になります。また、複数の孫がいる場合等、公平を欠いてしまいますとトラブルの元になりかねませんので注意が必要です。
⑤マイナスの財産がある場合

相続では、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぎます。親に借金があれば、子どもはその借金も引き継ぐことになるのです。
親子とはいえ、子どもが親の財産をすべて把握していることは、ほとんどないでしょう。むしろ、親からしてみれば、子どもにはあまり知られたくないという心理が働きます。それが故に、相続が発生した時に「親の財産を把握するのに苦労した」というのはよく聞く話です。
それが預金などプラスの財産であればまだ良いのですが、借金などのマイナスの財産があれば大変です。また、亡くなった人に借金がなくても、連帯保証人になっていれば、その義務も子どもが引き継ぐことになります。
プラスの財産もマイナスの財産も合わせて相続することを、「単純承認」といいます。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には「相続放棄」をすることもできます。また、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、プラスの部分だけ相続をする「限定承認」という方法もあります。
しかし、これらの手続きは相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。手続きがなければ「単純承認」したと見なされてしまいます。
葬儀等もありますので、3ヶ月以内に親の財産を1から全て把握しようとすると困難を極めますし、3ヶ月以上経過してしまってから、保証債務の存在を知っても、借金の存在を知ることができなかった正当な事由がない等、相続放棄が認められない場合も出てきます。
このように借金や連帯債務などがある場合には、子どもに想定外の苦労をさせないように遺言を残しておくべきでしょう。遺言を書くときには、財産を正確に把握し、それぞれを誰が継承するか明確にしますから、子どもは遺言書によって親の財産を一目で把握できます。
マイナスの財産がある場合、3つの相続方法のうち、どれを選択するか、判断がしやすくなります。また、遺言があれば遺産分割協議が必要なくなりますので、トラブル防止にも役立ちます。
⑥事業を営んでいる場合

事業を営んでいる場合、相続が発生すると、会社の財産も相続の対象となります。主な会社の財産と言えば、自社株と不動産ではないでしょうか。
これらは、個人の金融資産などと同様に遺産分割の対象となります。相続人が配偶者と子ども2人であれば、配偶者が半分、子どもは4分の1ずつを法定相続分として相続する権利が生じます。
親からしてみれば、「兄弟仲よく事業を盛り立ててほしい」と考えるかもしれませんが、それはうまくいかないケースが多いようです。兄弟に自社株が分散してしまうと、経営権も分散してしまいます。仮に長男が事業を引き継いだとしても、株主である弟にも発言権がありますので、何かと経営に口をはさんでくることが考えられます。
また、自社株を長男が相続したとしても、事務所や店舗などの不動産を弟が引き継いでしまえば、事業の継続が難しくなってしまうこともあります。弟がお金に困った際、不動産を売却してしまうなどの危険性があるからです。
事業を安定させるためには、自社株や事業用の不動産を後継者に集中させることが必要です。長男が後継者に決まっているのであれば、自社株や事業用不動産を長男に相続させるという遺言を書いておく必要があります。
その場合に問題になるのは、他の子どもに何を相続させるかです。長男だけに自社株を残し、他の子どもはほとんど受けるものがないというのであれば、やはりトラブルの元になってしまいます。
他に金融資産があればよいのですが、ない場合には、生命保険に加入して、その保険金を後継者以外に相続させるなど、代わりに相続させる財産を手当てしておく必要があります。
それはすぐに用意できるものではありません。保険に加入するのであれば保険料が必要ですし、健康状態によっては加入できないこともあります。時間をかけて計画的に準備する必要があります。
遺言でできること、遺言を書いた方がよい場合について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
通常でも診療でお忙しい開業医のみなさまは、「そのうち書こう」などと考えていると、なかなか書くことはできません。年齢を重ねて体力を失ってしまうと、余計に書く気力を失ってしまいます。
遺言は元気なうちに書いておくのが鉄則です。
今のうちに遺言書に取り組んでみてはいかがでしょうか。